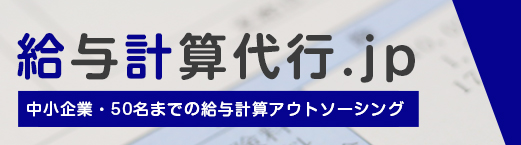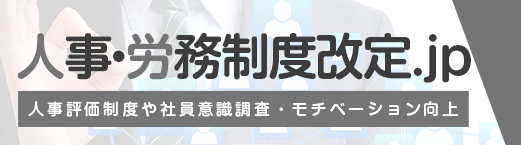従業員が増えてくると、様々な課題が出てきます。
その一つが「就業規則」です。
従業員が10人を超えると、就業規則の作成と届け出が法律で義務付けられます。
しかし、従業員数が10人未満の場合でも、就業規則を作るメリットはあります。
今回は、就業規則と従業員数の関係について、分かりやすく解説します。
10人未満の企業でも、就業規則作成のメリット・デメリットを踏まえ、最適な対応を考えてみましょう。
就業規則と従業員数!常時10人以上の定義とは
🔸常時10人以上とはどういう状態か
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業主は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。
では、「常時10人以上」とは、具体的にどのような状態を指すのでしょうか?
これは、一年を通して、平均的に10人以上の労働者がいる状態を意味します。
一時的に10人を超えたとしても、それが継続的なものでなければ、「常時」には該当しません。
例えば、繁忙期だけ従業員を増やし、それ以外は10人未満の場合、届け出義務は発生しない可能性が高いです。
ただし、判断に迷う場合は、専門家への相談がおすすめです。
また、この「常時10人以上」は、事業所単位でカウントします。
複数の事業所を持つ企業の場合、それぞれの事業所で従業員数をカウントし、10人を超える事業所があれば、その事業所ごとに就業規則を作成し届け出る必要があります。
企業全体で10人を超えていても、個々の事業所が10人未満であれば、届け出義務は発生しません。
🔸従業員数のカウント方法 正社員・パート・アルバイト・派遣社員はどう扱うか
従業員数をカウントする際には、正社員だけでなく、パート、アルバイト、契約社員なども含めます。
派遣社員については、派遣元企業との雇用関係にあるため、派遣先の事業所ではカウントしません。
休職中であっても、雇用関係が継続している従業員はカウント対象となります。
一方、経営者自身は、通常はカウント対象外です。
役員についても、労働基準法の適用を受けるか否かによってカウントの可否が判断されます。
役職名ではなく、実際の業務内容や権限を基に判断する必要があります。
🔸届出義務と罰則 違反した場合のリスク
就業規則の届け出を怠ると、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、労働基準監督署の監査時に指摘を受け、是正勧告を受けることにもなりかねません。
これは、会社の信用や評判にも悪影響を及ぼすため、届け出義務は必ず遵守する必要があります。
従業員の人数が10人未満の場合 就業規則は必要ない?
🔸10人未満でも就業規則を作るメリット
従業員が10人未満の場合、就業規則の作成は法律で義務付けられていません。
しかし、作成しておくことで、様々なメリットがあります。
まず、労働条件や就業規則を明確にすることで、従業員とのトラブルを未然に防ぐことができます。
例えば、労働時間、休暇、給与、懲戒処分に関するルールを事前に定めておくことで、後々のトラブルを回避できる可能性が高まります。
また、就業規則は、企業文化や理念を明確に示すツールにもなります。
従業員に会社の考え方を共有することで、一体感やモチベーション向上に繋がる可能性もあります。
さらに、将来的に従業員が増加した場合、既に就業規則が整備されていることで、スムーズな対応が可能になります。
🔸10人未満でも就業規則を作らないデメリット
就業規則がないことで、従業員との間でトラブルが発生しやすくなります。
特に、労働時間や給与に関するトラブルは、大きな問題に発展する可能性があります。
また、就業規則がないと、企業としての体制が整っていないという印象を与え、優秀な人材の確保が難しくなる可能性も考えられます。
🔸10人未満でも準備を始めるべき理由
10人未満の段階から就業規則の作成を始めることで、じっくりと自社に合った内容を検討することができます。
また、従業員数が増加する前に制度を整備することで、後々の混乱を防ぐことができます。
さらに、助成金申請の際に、就業規則の有無が審査の対象となる場合があります。
就業規則と人数に関するよくある質問と回答
🔸就業規則の作成・届出はどこに相談すれば良いか
就業規則の作成や届出に関して不安がある場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。
彼らは、労働基準法に関する専門知識を有しており、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
🔸就業規則作成にかかる費用は?
就業規則の作成費用は、依頼する業者や内容によって異なります。
規模の小さい企業であれば、比較的低価格で作成できる場合もあります。
ただし、複雑な内容や特殊な事情がある場合は、費用が高くなる可能性があります。
🔸就業規則の見直しはどのくらいの頻度で行うべきか
就業規則は、法律改正や会社の状況の変化に合わせて定期的に見直す必要があります。
一般的には、年に一度程度の点検を行い、必要に応じて修正することが推奨されます。
まとめ
今回は、就業規則と従業員数の関係について解説しました。
「常時10人以上」の定義や、従業員数が10人未満の場合の対応について、具体的な例を挙げて説明しました。
従業員数に関わらず、就業規則は企業運営において重要な役割を果たします。
トラブル防止や企業イメージの向上、そして将来的な成長のためにも、適切な就業規則の作成・運用を心がけましょう。
10人未満であっても、将来を見据え、早めの準備を始めることが大切です。
就業規則は、単なる書類ではなく、従業員と会社を守るための重要なツールです。